例年通り新刊本の振りかえりである。毎年、書き出しは色々と言い訳を書き連ねるのがならいであるが、2023年は公私ともに色々落ち着かず、読書への差し支えが顕著にあった。評判となった本で買いはしたが読めなかったという本も少なくない。諸般の状況を勘案し、今回は例年より本を絞り込んで取り上げることとした。
■日本政治・外交
境家史郎『戦後日本政治史―占領期から「ネオ55年体制」まで』(中央公論新社[中公新書])
中山俊宏『理念の国がきしむとき―オバマ・トランプ・バイデンとアメリカ』(千倉書房)
竹内桂『三木武夫と戦後政治』(吉田書店)
『戦後日本政治史』は副題通り、約80年の戦後政治史を300頁余りで描ききったもの。著者自身が断わるように、戦後政治理解の「筋書」を読者が得ることを目的とした本で、簡潔で要を得た新書らしい新書という内容となっている。とはいえその記述は無味乾燥どころか特色を明確に持つ。55年体制下の政治について自民党内の派閥対立などより、野党が対抗勢力として結集できなかった点により多くを割いている点、また全体として憲法に由来する保革の激しいイデオロギー対立と、政権交代可能性の低い政党配置を中核とする「ネオ55年体制」への道という見立てを提示している点などはそうした特色といえよう。バランスは十分に保たれているが、この時代に書かれた通史、という性格を強く持った本として印象に残った。
『理念の国がきしむとき』を日本政治・外交の項に入れるのは一見違和感があるかもしれない。2022年に亡くなった著者が2016年以降発表した時事的論考をまとめたもので、タイトルのとおり採録された論考の多くはアメリカ政治を論じたものである。
しかしこの項に本書を取り上げたのは、本書に取り上げられた「『衰退するアメリカ』のしぶとさ―日米同盟を『再選択』する」(2016年4月発表)が日本外交論・日米同盟論として優れて印象に残っていたからである。この論文は、アメリカが主導し構築された戦後国際秩序において同国の役割が低下していく中で、日本の目指すべき戦略や果たすべき役割、その中における「日米同盟」の意義を明確に論じたものであった。初出の論文集でこの論文を読んだ頃、私は前年に成立した平和安全法制をめぐる不毛極まりない外交・安保論議に倦んでいたが、慈雨のごとく感じられたのを覚えている。本書で再読してもそうした印象は変わることはなかった。アメリカを日本で論じるという仕事に尽くした、著者の真価を示す論文の一つであったと感じている。
『三木武夫と戦後政治』は明治大学所蔵の三木武夫関係資料、のみならず様々な史資料を駆使して三木武夫の政治的生涯を描いた大部の研究。どんな政治家も多面的な存在であるが、三木という人物の経歴を反映した本書の内容は一段と多岐にわたり、通読は容易ではない。しかしながら、理想主義と現実主義の間に生き、しばしば批判者か称賛者の極端な意見で描かれがちだった三木武夫という政治家について、様々な検討のきっかけを与えてくれる本だと感じられた。一昨年に刊行された五百旗頭真監修『評伝福田赳夫― 戦後日本の繁栄と安定を求めて』(岩波書店、2021年)と同様に、戦後政治家論の発展を示す一冊といえよう。
■外交史・戦史
岩谷將『盧溝橋事件から日中戦争へ』(東京大学出版会)
Wilson D. Miscamble(金谷俊則訳)『日本への原爆投下はなぜ必要だったのか』(幻冬舎メディアコンサルティング)
大木毅『歴史・戦史・現代史―実証主義に依拠して』(角川新書)
岩間陽子編『核共有の現実―NATOの経験と日本』(信山社)
『盧溝橋事件から日中戦争へ』は、1937年7月の盧溝橋事件の勃発から第二次上海事変、南京戦とその前後に行われた和平工作と1938年1月の近衛声明(「対手トセス」声明)に至るまでを描いた歴史研究。日中双方の動向に目配りをしながら、軍事衝突という状況下で各アクターが様々な選択を重ね、その相互作用がいかに戦争の長期化をもたらしたかを描いている。中国側の史料公開により、中国側が抗日戦争に関して決して日本に侵略されるがままの受動的な存在ではなく、時折積極性を示していた事実は近年の研究で指摘されていた部分だが、それが日本側の行動とどのように影響しあったかを描いている点は本書の興味深い部分である。また蒋介石の直轄軍の軍事的能力への過大評価が第二次上海事変という状況をもたらしたこと、直轄軍の実際にの作戦上の拙劣さが状況を悪化させたことなど、こうした次元の判断や評価がやはりその後の展開に影響したことに目配りがされている点も無視できない。
本書の筆致は抑制的で淡々としている。ただ同書の注(その殆どは史料の典拠を示す注である)を見ると日中のみならず米英、ドイツ、フランス、イタリア、ソ連と、関係したアクターの文書を博捜しており、文字通り目を見張るものがある。著者は「はじめに」において、日中戦争理解については様々な断絶があるという説明をした上で以下のように論じている。「そうした場合、取り得る一つの態度は、史料をして語らしめるというものである。しかし、これも個別の史料を選択する以上、不偏不党ではない。できることといえば、できるだけ多くの立場の史料に目を通し、それらを用いて、自身が主観的であることを意識しつつ、客観的な事実を探求する以外にない」(5頁)。これは歴史叙述において極めてオーソドックスな態度と言えなくもない。しかし言うは易く行うは難しであることもまたよく知られていることである。本書はそれを実践している希な例であるといえる。
本書に不満をあえて言うならば本書の最大の持ち味である抑制的な筆致かもしれない。相互作用によって生じる状況とその変化自体を主体とした描写に対して、本来は状況に翻弄されたアクターに過ぎない蒋介石のトリックスターぶりが目立ってしまうような部分の課題はあると思われた(新聞書評などにはそうした「誤読」をしたように思われるものも見られた)。とはいえこれはある意味致し方ないとは言えよう。いずれにせよ読めば読むほど凄みを感じるという一冊であった。
『日本への原爆投下はなぜ必要だったのか』はThe Most Controversial Decision: Truman, the Atomic Bombs, and the Defeat of Japanの全訳。原爆投下の解釈については様々な論争が存在するが、本書はいわゆる「正統主義」の観点から、トルーマンがアメリカ合衆国大統領としてなぜ原爆投下を決断するに至ったかを簡潔に描いており、米側の意思決定過程を知る際に非常に有益な一冊となっている。
本書の主張によれば、トルーマンは対日戦争の早期終結を望み、また高額の国家予算を投じた原爆開発計画の意義を示す必要を感じていた(前者に関連して言えばこの観点からトルーマンはソ連の対日参戦も期待していた)。こうした極めて内向きな理由によって、原爆投下は決定されたという。日本の降伏要因として原爆のみを強調している点や、その道義性を議論する部分など本書は首肯できない部分もあるが、トルーマンにとって当時の状況がどのように見えていたかについては、今年新版が刊行され、解釈論が先立ちすぎる印象を引き続き与える長谷川毅『暗闘』より説得的であると思われる。
『歴史・戦史・現代史』は精力的な著述活動を続ける著者が、2019年から23年まで様々な機会に発表した文章をまとめたもの。著者はやはり今年刊行した『戦史の余白』のように、様々な戦史を扱った著作を多数出版しているが、『歴史・戦史・現代史』はあとがきに「様々なベクトルを持つ多数の文章」と書かれているとおり、時事分析から書評、新聞への寄稿やインタビューまで、扱っている内容が幅広い。だがそういった小文集だからこそ軍事史・政治史という、歴史研究において最もクラシックな分野を手掛けてきた著者のスタンスが明確に示されているように感じられる。
とりわけ歴史研究のあり方を論じた「歴史家が立ち止まるところ」は、歴史小説の創造力のあり方を一方に、実証主義的な歴史学のあり方を逆の一方に置きつつ、本来後者に含まれるはずがなされるべき検証を怠ったものとして「俗流」歴史書を批判しており、副題の「実証主義」とは何かを正面から扱っており興味深い。以下に特に印象に残った部分を引用する。
「歴史家が立ち止まるところで小説家は跳躍するというのが、筆者の持論である。歴史家は自説を組み立て、検証し、史実を確定していく。しかし、研究テーマとなる事象が生起してから今日に至るまで、すべての史料や証言が百パーセント残っているわけではないから、どうしても詰められないところが出てくる。歴史家は立ち止まり、これ以上は断言できないと述べるしかない。だが、小説家は、その場所から跳躍をはじめる。歴史学的に確認された史実を踏まえ、想像力をめぐらせて、そこから先を書きすすめる。このとき、小説家が拠り所とし、また執筆の目的とするのは、深い人間理解であろう。……
(中略)
……けばけばしい原色の描写は、ときに読者を幻惑する。一方、味気ない、索漠たる事実は幻滅を感じさせるだけになる恐れもある。しかし、歴史の興趣は、醒めた史料批判にもとづく事実、「つまらなさ」の向こう側にしかないのである。たとえ読者の不満を招こうとも、わからないことはわからないといわざるを得ない。」(172、174頁)
最も印象に残ったものとしてこの個所を引いたが、本書ははしばしにストイックな歴史への態度が示された文章が登場する。歴史研究に臨む態度の重要性を深く印象づけられた一冊であった。
『核共有の現実―NATOの経験と日本』は、ウクライナ戦争の勃発後瞬間風速的に盛り上がり、一瞬にして沈静化した(ように見える)「核共有(Nuclear Sharing)」制度について、NATOの実態を検証した論文集である。わかったようでわからない(だからこそ様々な期待が膨らんだ)核共有の歴史的経緯と、その特殊性を明らかにしている本書の各論文を読むと、改めて核兵器という兵器の持つ特殊性を実感せざるを得ないと感じさせられる。門外漢にも平易に書かれた本書の議論を前提とせず、核共有を真剣に論じることは困難になったといえるであろう。
■社会
谷口功一『日本の水商売 法哲学者、夜の街を歩く』(PHP研究所)
ドナルド・ラムズフェルド(井口耕二訳)『ラムズフェルドの人生訓』(オデッセイコミュニケーションズ)
『日本の水商売』は「スナック研究会」代表として、スナックを多角的に考察してきた法哲学者によるスナック論である。2021年から22年にかけて、コロナ禍の中で各地のスナックを探訪した『VOICE』の連載をベースとしており、スナックの歩みを振りかえりながら、新型コロナウィルス感染症が「5類」に移行するまでの時期にそれぞれの店がコロナ禍とどのように対峙したのかを明らかにしている。
乱暴にまとめれば、本書は二つの側面を有しているといえる。一つはコロナをめぐる夜の街の同時代史である。コロナ禍初期から徹底的にマークされた夜の街、その中でも大きな割合を占めるスナックは、「迫害」といって良い扱いを受けた。本書はとりわけクラスターが発生したとされた店がどのような誹謗中傷に晒されたかを関係者の声で明らかにし、行政、そしてマスコミの当時の行動について、検証の必要性を強く訴えている。
二つ目には、スナックの社会的意義の確認である。日本列島を縦断し、多数の実在の店を扱う本書では、様々な理由でその地にスナックが生まれ、成長していった様子が活き活きと描かれている。そこには自らの地元に商いを生むためスナックなどを幅広く営む「非英雄的起業家」や、地域コミュニティを支えるために生まれたスナックなどが続々と登場する。著者はこうしたスナックのありようから、地元に根を張り、コミュニティを築く人々の重要さに注意を喚起する。通り一遍の「成功」「メリトクラシー」言説に物足りなさを感じるならば、著者のこうした主張には大いに共感するだろう。
本書を読んだころ、私は本年やはり刊行された、福田和也『保守とは横丁の蕎麦屋を守ることである コロナ禍「名店再訪」から保守再起動へ』(河出書房新社)を併読していた。『保守とは~』は、これまでの不摂生がたたり健康を大きく損ない、文筆活動も困難になった福田和也が、コロナ禍にかつて訪れた名店を探訪し、食べ、飲むことで自らの活力を取り戻そうとあがく様子を描いた『サンデー毎日』の連載の書籍化である。そこでは様々な飲食店がコロナ禍に苦しみながら、自らの店を守ろうと努力している様子が描かれており、福田がその姿に強い感銘を受けていることが伺える。同書はこの意味で『日本の水商売』と同じメッセージを発しているといえるだろう*1。
ここまでの説明を読むと非常に堅苦しい本に思えるが、本書は紀行文として極めて優れたものになっている点を同時に取り上げないわけにはいかない。各地の歴史や文化をひもときつつ、その地のスナックのあり方に言及する本書の文章の見事さは類書にないものであるといえる。なお著者は本年、法哲学についての従来の思索をまとめた論文集『立法者・性・文明―境界の法哲学』(白水社)も刊行しているが、同書の「あとがきに代えて」でもこうした著者の文章の魅力を味わうことができる。
『ラムズフェルドの人生訓』は2013年に原著が刊行された、著者が官民の様々な仕事を経る中でメモしてきた、実践的な処世訓の集大成である(本書の存在は溜池通信で知った。8月6日の項を参照)。ある程度自らが歳をとったせいか処世訓のようなものに関心が出てきたところ、それがあのラムズフェルドがまとめたものと言えば、読まずにはいられなかったし、その判断は間違っていなかった。自らのエピソードを交えつつ披露される格言は単純におもしろく、味わい深い。
このような優れた観察眼を持っていたにも関わらず、政治家としてのラムズフェルドの評価は必ずしも芳しいものではなかった。そのリーダーシップのあり方や判断に対する批判を、説得力を持って示した著作は枚挙に暇がない。そのような人間がこういう興味深い人生訓を示すことができる点を含めて、人間という存在のおもしろさに関心を尽きなくさせるものがあった。
■おわりに
本記事で取り上げた書籍(2023年刊行された書籍のみカウント)はここまでで12冊となる。本の感想というのはやはり書いた方がいいもので、自分がどういった本が好きなのかを再確認するところが多かった。
いささか後味の悪い終わり方となるが、この観点から「いただけない」と思った本を最後に取り上げて本記事を終える。松里公孝『ウクライナ動乱 ソ連解体から露ウ戦争まで』(筑摩書房[ちくま新書])である。
本書が興味深い内容を含む本であることはまず指摘しておきたい。ウクライナ政治を専門の一つとして来た著者は、2022年に始まったロシアのウクライナ侵略を、ソ連解体の際の不自然なウクライナの分離・独立、ウクライナの国内統治の混乱による国内分断の深まり、旧ソ連地域を庇護国として扱うことをやめたロシアの態度変化など、様々な形で表出したソ連解体の後始末としての「分離紛争」の一つであると指摘している。著者の指摘が戦争の要因として興味深いものを含んでいるのは事実であろう。個人的には「当時の満州は混乱しており、問題含みであった」と満州事変を正当化する理屈のように読めなくなかったが、とはいえ一般的なウクライナ戦争論に対し、本書がユニークな視点を提供していることは無視できない。
しかし、本書は極めて書籍としての出来に問題があると言わざるを得ない。約500頁の筆箱のような形状の新書の中には、無数の人名と地名が乱舞し、地図情報の提供は不十分である。文章はぼやき調の脱線も多く、結語に至るまで締まりがない(後述の『週刊読書人』インタビューによれば、「冒険活劇のような軽妙な日本語」とのことだが、文章の自己評価はつくづく困難であると思わざるを得ない)。本書を読むのはひたすら苦痛だった。著者の同僚二名が本書を称賛する書評を新聞に寄せているが、同僚としてのお手盛りか、テーゼのみに関心があり本としての出来に関心を持たなかったのだろうかという疑問を抱かざるを得なかった。
著者は『週刊読書人』2023年9月29日号の著者インタビューで、「『著者が注をつけることを諦めれば、学術書の内容を新書にすることができ、千円強で読めてお得感がある』というのがちくま新書のリーダーの戦略です」と語り、英語圏で発表した研究を日本語に還元するスタイルとしてこうしたスタイルが今後もありうることを示唆している。編集者自身の言葉でなく、著者の言葉であることを割り引く必要があるだろうが、仮に「お得感」の帰結がこの筆箱であるとしたら、ちくま新書は今後のあり方をよくよく考える必要があるだろう。2024年はあまりこうした本を読みたくないものである。
*1:この点に関する著者の主張は、下記の対談ではより鮮明に理解できるであろう。若田部昌澄・谷口功一「夜の街に集う権力者たち...地方のスナックがもつ“公共圏”としての顔」https://voice.php.co.jp/detail/10370?fbclid=IwAR0N9ccJ0EXI3XFYIvsyjnCpeHonJcfvS597YBT5-tkRFuc2c2C3r1U26UY
































































































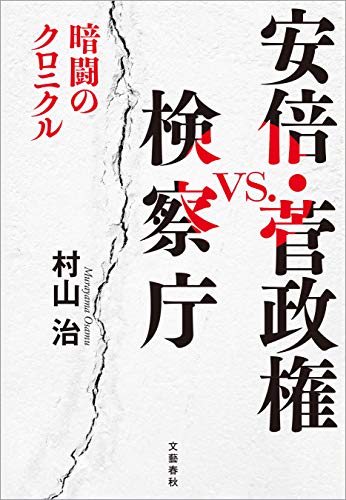









![日本外交の150年 幕末・維新から平成まで [ 波多野澄雄 ] 日本外交の150年 幕末・維新から平成まで [ 波多野澄雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2416/9784990122416.jpg?_ex=128x128)

![朝海浩一郎日記 付・吉田茂書翰 [ 河野 康子 ] 朝海浩一郎日記 付・吉田茂書翰 [ 河野 康子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1826/9784805111826.jpg?_ex=128x128)


















