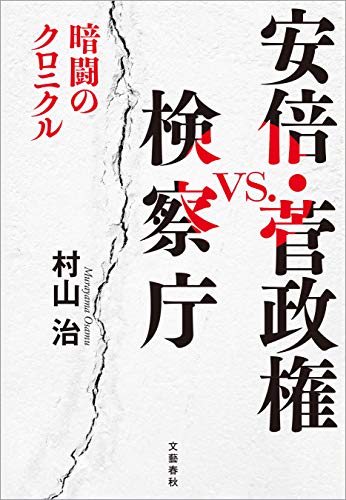2020年の本
過去のログを漁るとまるで言い訳の変遷がボージョレ・ヌーボーの評価のようであるが、本当に今年もろくに本を読まない一年であった。Twitterで報告したとおり、私事でも色々あり、世の中はコロナに見舞われた。在宅勤務が増える中で読書がはかどるかとも一瞬思ったのだが、そんなことはなく、人間は読書の習慣が鈍ると本を読まなくなるのだと反省の思いが強くあった。来年からは是正しなければならないとかなり深刻な反省を覚えるところがあったが、それはそれとして今年出た本で印象に残った本を取り上げることとする。
■印象に残る研究あれこれ
どのような脈絡をつけたものか考えたが、ランダムに取り上げることとした。まず一冊目として取り上げたいのは川名晋史『基地の消長 1968-1973 日本本土の米軍基地「撤退」政策』(勁草書房)である。本書は基地問題をめぐる政治学を研究対象としてきた政治学者が、1960年代後半に本格化した日本本土の在日米軍基地の再編・縮小政策の検討・実施過程を詳細に検討したものである。著者自身の研究テーマが示すように、本書の関心の対象は基地をめぐる政治である。
あくまで事例という位置づけであるが、本書は米政府の一次史料を詳細に分析することで、その政策がどのように進められたのかを明らかにする歴史研究としての性格を濃厚に帯びている。ペンタゴン及び各レベルの軍司令部に勤務する文民、軍人の双方からなる行政部門、さらに当時国防費の抑制や行政府の戦争権限肥大化に関心を寄せていた連邦議会による専門的検討などを仔細に追っており、米国における政治過程がどのように進むのかという点でも非常に教えられる点が大きかった。「基地の政治学」に関心のない私のこうした読みは著者の自身の関心からすれば本意ではないかもしれないが、そうしたファクトファインディング的な示唆も大きな一冊であるといえよう。
また本書が示唆しているとおり、この基地の縮小・再編が向かった先がどこであったかといえば、それは返還以前の沖縄であった。米軍の基地機能を沖縄に集約するまでの展開、さらにその後についても、これを平易に理解できる野添文彬『沖縄米軍基地全史』(吉川弘文館)が出版された。これもまた教えられるところが多かった。
さて、2020年は戦後75年でもあった。微妙な節目であることもあり、戦後70年のそれに比べて特に目を引く出版物は少なかったように感じたが、その例外として富田武『日ソ戦争 1945年8月』(みすず書房)が取り上げられよう。「ソ連の満州、千島・樺太侵攻」などと表現される1945年8月以降の日本とソ連の軍事衝突を「日ソ戦争」という言葉で捉えた一冊である。日ソ両軍の軍事行動、邦人を襲った悲劇(ソ連軍による蛮行)、抑留者をめぐる戦後処理など、従来個々に論じられてきたテーマが統合され、一つの戦争の過程として論じられており、読み応えのある一冊である。
私事になるが祖父が抑留経験者であったこともあり、「日ソ戦争」には強い関心がある。率直にいって本書は読んでいて気の滅入る一冊であったが(気の滅入らない「日ソ戦争」本などないが)、読み応えのある一冊であった。なお著者はfacebook上で「抑留研究会」を主催して精力的に発信を行っており、これも一読の価値がある。
周年的なものといえば、今年はインドネシアにおける9・30事件(1965年)から55周年の節目でもあった。これに関連したものともいえる本として、倉沢愛子『インドネシア大虐殺―二つのクーデターと史上最大級の惨劇』(中央公論新社/中公新書)、同『楽園の島と忘れられたジェノサイド―バリに眠る狂気の記憶をめぐって』(千倉書房)の二冊が出版された。同著者の2014年刊の『9・30 世界を震撼させた日―インドネシア政変の真相と波紋』(岩波書店)に続く一冊だが、1946年生まれのインドネシア地域研究者である著者が、インドネシアの政治的方向、さらに東南アジア地域の動向も一変させたこの事件に歴史的事件として関心を寄せると同時に、当時同時代を生きながら十分な関心を向けてこなかったとの使命感をもとにものしたものである。
いずれも史料の検討と共に、虐殺の過程を明らかにするため多くのインタビューなど実地の調査を反映しているが、概説書である『インドネシア大虐殺』以上に『楽園の島と忘れられたジェノサイド』の与える印象はより強い。人口160万人のうち、5パーセントにあたる8万人という最も苛烈な虐殺が行われたバリ島の虐殺過程と、その後も続いた迫害と和解の困難、「楽園」という観光地イメージの与える制約など、9・30事件が一つの地域に与えた影響をミクロに考察しており、興味深い一冊である。装丁の美しさもそうした点を引き立てているといえよう。
ところで、現場を踏まえた考察という点でやはり印象深かったのは、濱田武士・佐々木貴文『漁業と国境』(みすず書房)であった。領土問題をめぐって海洋問題が議論されることは中国の海洋進出が活発化する中で多くなり、海洋資源保全の観点から漁業に言及されることもまた多くなった。一方漁業経済学を専門とする著者らは、本書で日本の漁業をめぐる国際関係に着目しており、北方水域、日本海、東シナ海、南太平洋と、いずれにおいても日本の漁業が極めて困難なトラブルに日々見舞われていることを明らかにしている。ロー・ポリティクスの問題として漁業権益をめぐる問題はしばしば歴史的にも注目されてきたテーマであり、その点で本書は古典的なテーマを扱っているともいえる。とはいえ、領土をめぐる日本外交の緊張が日々増している裏側で、それがどうなっているかの現在地を知ることができる一冊と感じられた。
また概説書になるが、今年はドイツ統一30年を受けて、アンドレアス・レダー(板橋拓己訳)『ドイツ統一』(岩波書店/岩波新書)も出版された。ドイツ現代史をテーマとする概説書の出版・翻訳は続いているが、ドイツで出版された概説書を翻訳した本書は、解説の充実も相まってこのテーマに暗い人間としてはありがたい一冊であった。ドイツ史に限らず西洋史についてはかつてのように日本における研究者層の厚みが失われていることがしばしば指摘されているが、こうした概説書の翻訳出版はそうした部分の底上げをもたらしてくれるものだと感じられる取り組みでもあった。
また、今年の無視できない一冊として、谷口将紀『現代日本の代表制民主政治―有権者と政治家』(東京大学出版会)が出版されたこともあげられよう。2003年以来継続的に東京大学と朝日新聞によって実施された有権者・政治家調査データをもとに、政治家と有権者が、どのような政策を重視し、またどのような政治傾向を持っているのかを明らかにしている。都度の調査結果については、朝日新聞や総合雑誌で都度その内容を見た記憶があるが、20年弱を総括する形で示されているのはまさに貴重な成果といえるだろう。本書はその考察の結論として、欧米諸国などにおいて大きな政府・小さな政府といった社会経済体制をめぐる選択が重要な政策的争点として認知されるのが一般的であるのに対して、日本において重視されるのが、憲法や安全保障問題、原子力エネルギー問題であったという見解を示している。今後の日本政治の展開を考えるうえでも、その前提として考えたい一冊でもあるといえよう。
■評伝・回想録
評伝・回想録としてまず言及したいのは、駐英大使、国際交流基金理事長などを歴任した外交官である藤井宏昭の回想録『国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ―藤井宏昭外交回想録』(細谷雄一ほか編、吉田書店)である。正直なところ、官僚の回想録は「こういう本だ」と説明するのは通常難しい。転勤・異動の多いキャリア外交官なら猶更である。しかし本書は、1956年に外務省に入省、要職を歴任したのち、97年に駐英大使で退職した著者のキャリアが、戦後日本が外交的な地位を回復し、拡大する過程と重なる形で描かれており興味深く読むことができる。特に日中国交正常化をはじめ、様々な外交的事件と直面した大平正芳外相の秘書官時代、昭和天皇訪米のセッティング、駐英大使時代の日英和解の推進などは、興味深く読めるところであろう。本書は暴露本的でも、また晦渋な学術書風でもない。しかしながら書くべきことは書かれているし、おそらくそうでないものは捨象されている。憲法前文の一節である「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」が自然に感じられる、読後感のよい一冊であった。
ほかに回想録として印象的だったのは、浅川雅嗣(清水功哉聞き手)『通貨・租税外交―協調と攻防の真実』(日本経済新聞出版)である。財務官という第一線を退いて間もない著者が内幕も含むインタビューに応じるという点で異例の一冊だが、欧米圏の文化に倣った一冊という趣旨とのことであり、内容を理解できたかはともかく、その取り組み自体が興味深いものであった。
評伝としては、大木毅『「戦車将軍」グデーリアン―「電撃戦」を演出した男』(角川書店/角川新書)があげられよう。大木氏の近年の著作と同様に、最新の研究成果を踏まえつつ、「電撃電」の構想者として知られてきたハインツ・グデーリアンの実像に迫る一冊である。本書で下されるグデーリアンへの評価は、政治的にナチズムに接近してその弊害に目をつぶり、また手塩にかけた装甲部隊の権益維持に汲々とし、戦術的な能力は優れているが、戦略眼を持たない軍人という厳しいものであるといえる。その評価は極めて厳しいものであるといえるが、「なぜドイツは敗戦したのか」を考えうる点で、人物というミクロから改めて接近できる一冊であった。
なお著者は、自らの回想録ともいいえる戸高一成氏との対談集『帝国軍人―公文書、私文書、オーラルヒストリーからみる』(角川書店/角川新書)も今年出版している。本書は旧軍人の集う団体のスタッフとして、また歴史雑誌の編集助手として、将官を含む旧軍人と触れてきた二人による戦後の旧軍人と旧軍をめぐる対談集だが、実地の旧軍人を見知っているだけに、軍人評を行いながら、軍隊の残した記録、回想を読む時に注意すべき事項や留意すべき組織特性を縦横に語ったものとなっている。
もちろん、実際に軍の遺した一次史料を読んで研究や調査を行う人間はまれだろう。しかし本書は、そうしたことをする人間でなくても(一般の書籍やドキュメンタリーを見る人間であっても)、どんな想像力を働かせてこうした時代や組織を考えればよいかというリテラシーを与えられる一冊だと感じられた。こうしたリテラシーというのは本来何らかの形で「わかっている人間」から手ほどきを受けるというのが望ましいのであろうが、なかなかそういうことは難しいものである。それが活字という形で基礎的に提供されているというのは、貴重なことだと思われる。
■ドキュメンタリーあれこれ
いくつか取り上げることが可能であろうが、まず村山治『安倍・菅政権vs.検察庁―暗闘のクロニクル』(文藝春秋)を取り上げたい。本書は検察庁法改正問題、黒川弘務東京高等検察庁検事長の賭けマージャン辞職をクライマックスとする、第二次安倍政権官邸と法務・検察間の幹部人事をめぐる数年間の抗争のドキュメントである。「政権の守護神」として安倍官邸を守ってきた検事・黒川の検事総長就任を阻止する…そういう風に盛り上がったのがかの騒動であったと思われるが、検察を記者として長く追ってきた著者は、黒川と検察官任官同期の林真琴(現検事総長)の来歴と法務・検察がこの間のどのような状況に置かれていたかを論じつつ、2020年に至るまでの長い伏線を明らかにすることで深層に肉薄している。本書が明らかにしているのは、この問題の根幹は従来独立王国を築いてきた法務・検察という組織と、法務・検察も含めて政治主導を当然とする安倍官邸(特に人事を最大の権力資源としてきた菅内閣官房長官)の人事をめぐる闘争であったということである。
本書を一読して感じたのは、この騒動も著者のような長いスパンでとらえると、90年代以降の政官関係の変化の中で生じた問題であること、また法務・検察という一般の官庁とは若干性格が違うがゆえに、そうした政治優位への反応の遅れた組織がそれにどう対応するのかという問題に翻弄されたという話ではないかということであった。人事、人の評価というものは様々であり、関係者の中にはまた違った物語もあるのかもしれない。とはいえきわめて興味深い一冊であったといえる。
またもう一冊取り上げたいのは、駒木明義『安倍vs.プーチン―日ロ交渉はなぜ行き詰まったのか?』(筑摩書房)である。本書は安倍政権が意欲的に取り組みながらも、なんらの成果も残せなかった対ロシア外交(領土・平和条約交渉)について、朝日新聞の記者として取材にあたってきた著者がその失敗の理由を詳細に明らかにしている。
特に著者が指摘しているのは、2000年代半ばよりロシア側の領土・平和条約問題をめぐる態度は日本側と調整困難なものへと硬化しつつあり、安倍政権期においてそれは鮮明なものとなっていたという事実である。それにも関わらず、安倍政権は楽観的な見通しのもと、国内のマスメディアに楽観的、かつ情緒的な見通しを述べながらロシアとの交渉に突き進んでいったと厳しく批判している。
本書の展開するロシア外交の分析、そして安倍外交批判は極めて説得力があると感じられるものであった。また同時に興味深いと感じられたのが、本書でロシア側の論理を分析する際に、ロシア語に長けた著者自身の取材だけでなく、記者会見やテレビ番組、公的発表といったいわゆる公開情報も豊富に用いていることである。
逆を言うと、公開情報を駆使すれば、ロシア側の態度は明瞭であったことが本書では明らかにされている。にもかかわらず、なぜ安倍外交はあれほどロシアに熱を上げていたのだろうか…。著者はこの問いには答えていないが、その点が根本的な疑問として湧き上がる一冊でもあった。
どこで取り上げるか悩んだが、本節の最後に取り上げることにした一冊は、佐藤栄作政権下に日中国交正常化に関わったとされていたが、その存在を含め一切が謎に包まれていた江鬮眞比古(えぐち・まひこ)の人物とその行動に迫ったドキュメント、宮川徹志『佐藤栄作 最後の密使―日中交渉秘史』(吉田書店)である。沖縄返還交渉に携わった外交官・千葉一夫の評伝をものしたNHKのディレクターが、2017年にNHK・BS1スペシャルで放送された内容に更なる調査を加えた本書は、率直に言って、「まだこんな事実が明らかになるのか」という新鮮な驚きを感じさせられた一冊であった。その証拠となる総理秘書官・西垣昭の日記など詳細な資料編も含めて刊行された本書は、うれしい不意打ちといえる一冊であったといえよう。
■各種書籍化について
文庫化をはじめ、書籍化されたことがうれしかった本について今年も触れたい。文庫化は好きだった本、関心を持っていた本があらためて文庫として息を吹き返す、という点でうれしいものである。安価に人に薦められるのもうれしいところである。その点では以下の三冊が特に文庫化がありがたい本たちであった。
また論文集としては、戸部良一『戦争のなかの日本』(千倉書房)、黒沢文貴『歴史に向きあう―未来につなぐ近現代の歴史』(東京大学出版会)の二冊が印象に残った。いずれも掲載論文の多くは過去に関心を持って読んでいたものだが、それが書籍としてあらためて世に出るというのは素晴らしいことと感じられた。
■終わりに
例年通り雑駁な感想文の連なりとなったが、最後に取り上げたいのは、待鳥聡史『政治改革再考―変貌を遂げた国家の軌跡』(新潮社/新潮選書)である。本書は、日本国内で平成の時代である90年代以降急速に進んだ統治機構に関わる各種の改革―選挙制度、行政機構、中央銀行、司法・地方分権など―を概観すると共に、それがいかなる相互作用をもたらしたのかを論じた、平成の諸改革の総決算ともいえる分析であったといえるだろう。
ただ、本書の内容それ自体より面白く感じられたことがあった。本書を読み始め、この本はたまたまその直前に読んでいた、村松岐夫『日本の行政―活動型官僚制の変貌』(中央公論社/中公新書)と対になる一冊であることを発見したことである。
1994年に出版された村松の本は、日本の行政の歴史的経緯と現状を論じつつ、その抱えている課題を明らかにし、今後の変革期において、何を変化させていくべきかを論じている。そしてそこで指摘されている項目こそ、待鳥の本で取り上げられている諸機構・制度の改革であった。同書は官僚制の改革の必要性を指摘しながら、そのためには日本の政治システム・統治機構の包括的な改革が不可欠であることを述べていたのである。
興味深かったのは、村松が最後に「市民」という項目を設け、いわゆる有権者の現状と、これからの市民に期待される政治・行政への態度を論じていた点であろう。これは待鳥の本からは消えていた要素であった。もちろん待鳥の本の目的は実際に行われた諸改革の総括であるから、それの有無を論じるのは目的でないかもしれない。しかしこの二冊の本の間にある違いはなんであろうかと、しばし考えるところがあった。